そして、夜が明けた。ヒスイは身支度を整え、席につく。両脇にはエバとセフとがいた。
「あー……」
エバはしきりに自分の髪を撫でつけ、不機嫌そうに声を漏らしている。リリスの催眠術にかけられたあと、眠りこけていた三人は服を剥かれ、水を浴びせられて今日に至ったわけである。リリスは
「行水がわりよ」
とにこやかに言っていたが、実質は洗濯されたのとさして変わらない。ちゃんと手入れをしないと、エバの髪の毛はすぐにこんがらがってしまうらしい。
そんな妹の様子を、姉のリリスはにやにやしながら見つめていた。リリスのような性格の人間にとって、エバはもっともいじりがいのある相手なのだろう。
「さて……作戦会議を始めるとするかの」
全員の準備が整ったのを見計らい、イェンが咳払いする。おもむろに一枚の地図を取り出すと、それを円卓の上に広げた。
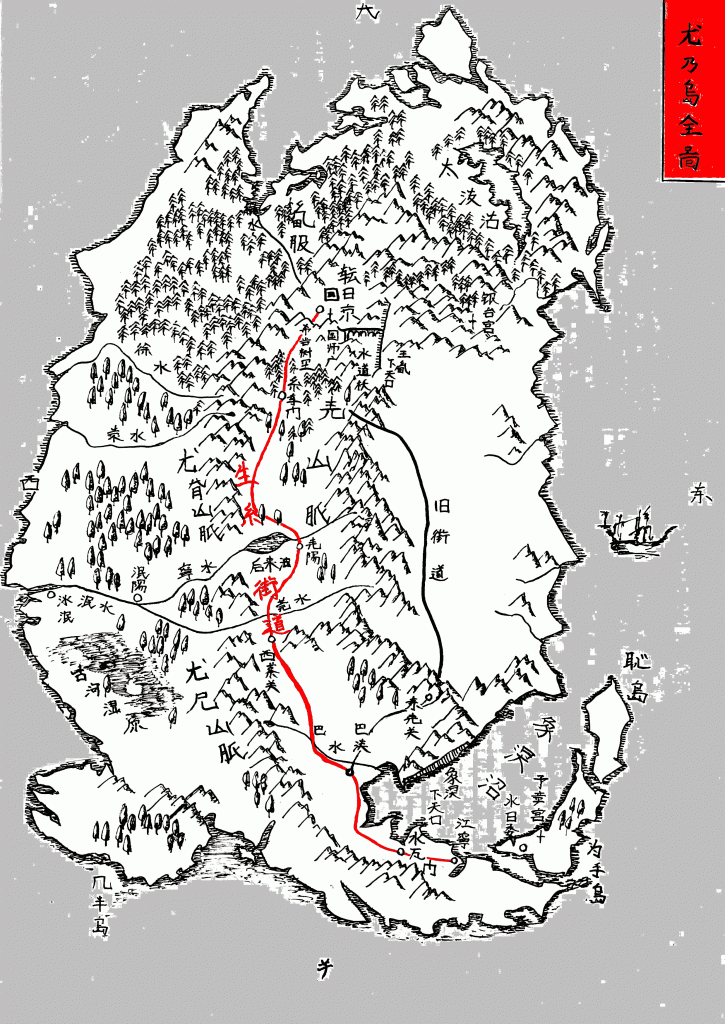
(これが……)
他の四人にとっては平凡な地図でも、記憶のないヒスイにとっては新鮮なしろものだった。泰日楼の名前は、島の遥か南にある。そして王都は――、
「ヒスイ、ここよ。ここが王都」
探しあぐねているヒスイの様子を察して、エバが王都の位置を指し示した。
「転日京――」
「そうじゃな、まずはそこから説明すべきじゃった」
イェンがあらためて、転日京の位置を指し示した。それは島のちょうど中央から、すこしだけ北にずれた方角にある。
「予章宮から本島まで渡るじゃろ? あとは生糸街道を通って行けば転日京まで繫がっているわけじゃから、ほとんど一本道じゃな」
「一本道な分だけ、塞いでいる敵は一から百まで全部相手にしなくちゃいけないんだけどね」
茶をすすりながら平然と言ってのけるリリスに対し、エバもセフも不安の色を隠さなかった。
「まぁ、それはたいした問題じゃないのじゃ。どうせ妾とリリスとで片っ端からやっつけるから」
「庭の雑草は全部抜いておくから」程度のお気楽な口調でイェンは答える。――がしかし、この二人ならばきっとやってのけるだろう。辺りをうろついているだけの氓などはものの数でもないだろうし、飛び交っている翩であってさえも、リリスが蚊トンボのごとく叩き落すのだろう。
セフが不安げにイェンに尋ねた。
「じゃあ……問題は何なんですか、老師ラォシ?」
「ヒスイをどうやって王都まで運ぶか、じゃ」
「どうやって、って……」
答えの真意が分からず、エバが口を挟む。
「普通に着いて行けばいいんじゃないですか?」
「それがうまくいけばいいんじゃが……」
「――何かあったわけ、イェンさん?」
顔を見合わせているイェンとリリスとに対し、ヒスイが尋ねた。
「私たちが寝ている間に、とか?」
「そうなのよ。察しがいいわね、ヒスイちゃん」
と言うと、リリスが指を「パチン」と鳴らす。すると包の天井が透け始め、とうとう透明になった。
「す、すごい……」
と、セフが感嘆の声を漏らしている。だがヒスイは、他に気になるところがあった。
「天蓋が――」
ヒスイが以前目にしたときよりも、空に張られていた瑠璃色の結界が濃くなっていたのだ。それこそ、空間全体が群青色に染め抜かれているといった有様だった。
「昨日の夜中じゅう、魔法による攻撃にさらされていてね――」
急須が勝手に動いて、リリスの茶碗に茶が注ぎなおされる。
「朝起きたときには、三枚張っておいたはずの結界の一枚目がはがされていたのよ。二枚目も傷だらけ。サイファが転日京にいるのだとしたら、ここまで届くんだから相当強烈な魔法よ。……ハァ」
ここまで話すと、リリスは露骨にため息をついた。
「用心しておいたけれど、まさか破られるとまでは思わなかったわ。私も不覚をとったものね」
表情にこそ出さないものの、自分の結界がサイファに破られたことが、リリスにとっては相当不愉快だったのだろう。
「それで、今は前のよりももっと強烈な結界を張ったわけだけど、どうもサイファの魔法は、ヒスイちゃんを直接狙っているようなのよ」
「私を……ですか?」
「そう。強烈な魔法をピンポイントでヒスイちゃんに投じている、ってわけ」
「――あいつらしい、狡猾なやり方じゃな」
リリスに続けるようにして、イェンが口を挟んだ。
「要するに、サイファは転日京から動かずに、ヒスイを狙っておるわけじゃ」
「あの手の魔法は、距離が近づくほどに強烈になるのよ。結界を張ってヒスイちゃんを守りつつ、転日京へ進軍するのは、さすがの私にも堪えるわ」
エバのうめき声が、ヒスイの耳にも届いてきた。イェンと一緒に行動することはできない。かといって離れ離れになったら、ヒスイはひとたまりもないわけである。現にサイファの魔術は、ここまで波及しているのだから。各地に異形がうごめいている以上、辛抱し続けることもできない。話を総合するかぎりでは八方ふさがりのようだった。
「でもね、方法がないわけではないのよ」
◇◇◇
「姉さん、それ本当なの?」
いぶかしげな口調で、エバはリリスに尋ねた。
「本当じゃ、エバ。――ヒスイに、下天を通ってもらうのじゃ」
イェンが「下天」という単語を口にした途端、両隣にいたエバとセフが身じろいだのをヒスイは感じ取った。
「下天を?!」
「そんな――えっ?」
エバとセフの反応はほとんど同時だった。
「老師、でも、下天って――」
「イェンさん、本気で言っているわけ?!」
「ああ、本気じゃ」
イェンは腕を組んだ。
「イェンさん、”下天”って――」
「ここじゃ」
と、イェンは地図の端をつまんだ。どうやら、大きな地図の上にもう一枚、小さな地図が重なっているようだった。イェンはそこを摘んで引っ張る。島の東側が捲れ、下から別の地図が出現した。地形を表す絵や記号は何もない。島の東岸をなぞっただけの空白がそこにあるだけだった。赤い文字ではっきりと「下天」と書かれている。
「アンダーグラウンドってところかしら?」
地図を解釈しかねているヒスイに、リリスが説明を添える。
「島の東側は二層式になっているのよ。この“下天”の上にもう一個の地層……つまり“上天”が重なっているの」
「洞窟……とは違うんですか?」
「うーん……。まあ洞窟みたいなものなんだけど、その、馬鹿でかい台地の中を思いっきりくり抜いた、っていうか。……上天という、土で出来た巨大な天蓋ドームを、下天に被せた、っていうか、そんな感じのところよ」
「でも、でも、危険すぎるって!」
喰ってかかるかのような剣幕で、エバが口を出した。
「あたし知ってるわよ、あそこに入った人たちは、誰も生きて帰ってこないって、だから中に入ることはおろか、入り口に近づくことも禁止されているって――」
「禁止してるのは妾じゃ」
「でしょ――えっ?!」
エバの目が点になる。固まってしまったエバに代わって、セフが続きを催促する。
「老師、それはどういうことですか?」
「いろいろあったんじゃが、とにかく禁止の命令を出したのは妾じゃ。むろん国師様の同意の上でじゃがの。禁止を解けるのも妾しかおらん。それにじゃ――」
次の言葉を発する前に、イェンは一呼吸おいた。
「それにの、あそこを通って無事だった者を何人か知っておる。――勇者様たちと、妾じゃ」
包の中は一瞬、水を打ったように静まり返った。世界に平和をもたらすために、勇者の一向は下天を通り抜けていったのだ。
「むろん、危険がないというわけではない」
沈黙するヒスイたちを前にして、イェンは静かに口を開いた。
「平時じゃったら、妾もこんなとっぴなことは考えなんだ。じゃが事態は深刻じゃ」
「勇者様御一行と状況は同じよね」
リリスは話を進める。
「……どこにいたって危険なわけ。サイファがどこからでも魔法を打てるのだとしたら、事態は勇者様のときよりもっと悪いかもしれない。ならばわずかであっても、可能性にかけるしかないわ。下天に入ってしまえば、さすがのサイファもヒスイちゃんの跡は追えなくなる」
リリスが語っている間、夜に見たイメージがヒスイに蘇ってきた。銃を握ったときに現れた、五感の全てに訴えかけるイメージだ。あのときのイメージが、もしヒスイを導いているのだとしたら――。
「イェンさん…… “下天”には塔が建ってなかった?」
「なんじゃと? どうしてそれを――?」
「昨日の夜――銃を握りしめたときに見たのよ。薄暗い中に……樹木と、塔がひしめいている幻影を。イェンさん、“下天”がどんなところか私には分からないけれど、私はそこを通らざるを得ないんだと思う。――“下天”に呼ばれているのよ。今ならそうだって分かる」
「フフフ……」
ヒスイが言い終わらないうちに、イェンは小刻みに肩を震わせて笑っていた。
「まったく、『私という親にしてあなたという子供』とは至言じゃな。母親の通った道を、娘が通るのじゃから」
「笑っている場合じゃないわよ、イェンさん。ヒスイちゃんが通れる勝算はあるわけ?」
「この場合必要なのは心の強さじゃ、リリス。ヒスイにはそれがある。……これでもずっとヒスイの面倒を見ておったからの。大丈夫――無事ヒスイが転日京へ辿り着けるように、妾も全力を尽くす」
「ねぇ、ヒスイ――ヒスイの見た幻影の中に、あたしもいた?」
エバがヒスイに尋ねる。エバの金色の瞳は、強く訴えかけるようにヒスイをまっすぐと見つめている。
「……それを聞いてどうするつもりかしら、エバ?」
ヒスイが答える前に、リリスが口をはさんだ。
「姉さん、あたしもヒスイと一緒に行くわ……ヒスイが目にするものと同じものを、あたしも見てみたいの」
「わたしも……!」
セフもはっきりと口にした。
「わたしも行きたい。役に立てるか分からないけど、わたしはあいつに……サイファに用がある」
セフの言葉からは静かな怒りが伝わってきた。
「うん……ヒスイちゃんはどうなの?」
エバとセフ、二人の様子を交互に眺めていたリリスは、最後にヒスイを見て訊ねた。
「私も……」
ヒスイは頷く。
「私も……二人に来て欲しい」
「イェンさんは? ――勇者の娘のお供なんていうの大役に、二人が務まると思う?」
「務まる」
イェンの声に迷いは無かった。
「ヒスイが二人と行く、と言っておるのじゃ。妾はそれを信じるだけじゃ」
「そう? じゃあ……決まりね」
「決まりじゃ」
リリスが組んでいた手を叩き、立ち上がった。イェンは最後に一度、深く呼吸をすると、ヒスイを見つめて言った。
「さぁヒスイ、来るのじゃ。――出発まで時が無い。伝えたいことは山ほどあるでな」